
新入荷
再入荷
上品スタイル 楽天市場】小川長楽の通販 その他
 タイムセール
タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(※)
999円以上お買上げで代引き手数料無料
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
商品詳細情報
| 管理番号 |
新品 :67188140444
中古 :67188140444-1 |
メーカー | 79cd5bbbe8c | 発売日 | 2025-04-12 07:43 | 定価 | 45000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||






















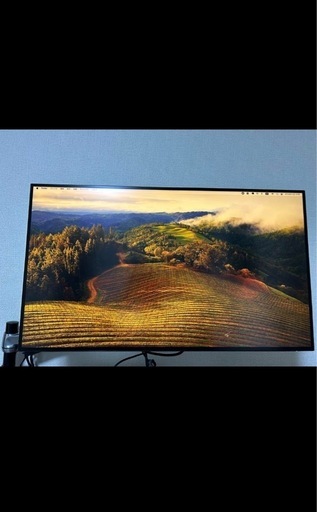










1874年明治07年 小川左右馬方眼源正幸の次男として丹波(現 亀岡市千歳町)に生まれる
1886年明治19年 楽家11代慶入氏の弟子となる
1906年明治39年 長楽 建仁寺代04代管長武田黙雷老師より「長楽」を、裏千家:円能斎宗匠より「長友軒」の号を賜る
1906年明治39年 同時に、楽吉左衛門師より、独立し「長楽窯」を五条坂八幡宮畔に開窯
1939年昭和14年08月 初代長友軒長楽65才にて没
【2代 小川長楽 (本名 幸一)】
1912年明治45年生まれる
1939年昭和14年10月 初代没・11月二代長楽を襲名する
1940年昭和15年 裏千家今日庵14世淡々斎宗匠の推挙にて建仁寺派第5代管長古渡庵頴川老師より「景雲」の号賜る
1943年昭和18年 芸術保存作家の指定を受ける
1955年昭和30年 芸楽釉楽窯による、白薬・焼貫七彩釉の 焼成に成功する
1991年平成03年 享年78歳にて永眠する
現在は、次代の3代目 小川長楽氏が窯を継承
【3代 小川長楽 (本名 幸夫)】号 裕起夫 長楽・松風軒
1947年昭和22年 2代の長男に生まれる
1966年昭和41年 工房・住所を山科清水団地に移り、師:長楽に師事
1969年昭和44年 号 裕起夫にて創作活動に入る
1977年昭和52年~1982年昭和57年の間、京都陶磁器青年会会長を務める
1989年平成01年 2代長楽喜寿を記念して親子展を開催
1991年平成03年 2代長楽 享年七十八歳にて永眠する
1992年平成04年 幸夫氏が3代長楽を襲名。同時に醍醐寺座主麻生文雄硯師より「松風軒」を賜る
1993年平成05年 徳仁親王と小和田雅子氏のご成婚を奉祝して、総本山醍醐寺の依頼により赤・白一双茶碗を献上
1995年平成07年 開窯90年4を祝して仁和寺門蹟・吉田裕信鯨氏より「楽焼おちゃわんや」の暖簾を賜る
現在 日本工芸協議会副会長
(社)京都国際工芸センター常任理事
清水団地(協)常任理事
------------------------------
【小川裕嗣(ひろつぐ)】※4代目:次代の作家
1978年昭和53年 3代の長男として、京都に生る
2002年平成12年 京都市産業技術研究所工業技術センター(陶芸家)修了
2003年平成13年 名古屋造形芸術大学(彫刻)卒
2004年平成14年 京都府陶工高等技術専門校を卒業、度維持に3代長楽に師事
2013年平成25年 「京焼、技と美の継承展」佐川美術館に出品~以後個展(京都大丸)(日本橋三越本店)を多数予定
------------------------------
【楽焼】<小学館より参照>
【初代 長次郎】
【2代 常慶】
手捏(てづく)ねで成形し、低火度で焼いた軟質の陶器。
天正年間(1573~1592)京都の長次郎が千利休の指導で創始。
赤楽・黒楽・白楽などがある。
2代 常慶が豊臣秀吉から「楽」の字の印を下賜されて楽を家号として以降、楽家正統とその傍流に分かれ、前者を本窯、後者を脇窯という。
【15代 楽 吉左衛門(らく きちざえもん)】陶芸家
1949年昭和24年己丑~京都府に生
師匠 父の、14代 楽吉左衛門の元研鑽中
------------------------------
【初代 長次郎】
【2代 常慶】
手捏(てづく)ねで成形し、低火度で焼いた軟質の陶器。
天正年間(1573~1592)京都の長次郎が千利休の指導で創始。
赤楽・黒楽・白楽などがある。
2代 常慶が豊臣秀吉から「楽」の字の印を下賜されて楽を家号として以降、楽家正統とその傍流に分かれ、前者を本窯、後者を脇窯という。
【15代 楽 吉左衛門(らく きちざえもん)】陶芸家
昭和24年己丑~京都府に生
師匠 父の、14代 楽吉左衛門の元研鑽中
------------------------------
【初代 小西平内(こにし へいない)】 陶芸家 楽焼 太閤窯
窯印 五三の桐の判
1899年明治32年 愛媛県生まれ
若くから大阪にでて、独学で楽焼を習得
1931年昭和06年 神戸有馬温泉に窯を築き茶陶を作ったもの
また、甲子園ホテルで庭焼を初め、川喜田半泥子に認められる
1956年昭和31年 五島慶太の推薦を得て渋谷東急東横店で個展
1958年昭和33年 兵庫県西宮市甲山に移窯
1964年昭和39年 太平を名乗り隠居
1991年平成03年 没
【2代 小西平内】陶芸家 楽焼
1928年昭和03年 愛媛県に生まれる。
1946年昭和21年 太閤窯を築いた初代小西平内に師事して作陶の技法を追求する。
1947年昭和22年 津市の川喜多半泥子に師事するため、津市長谷山のふもとの広永窯へ行き、半泥子の教えを受ける。こうした作陶生活が数年続く
1964年昭和39年 2代 小西平内を襲名すると共に、太閤窯を継ぎ、西宮市の甲山で作陶を続ける。
1964年10月 大阪三越で初めての個展を開き、以後、東京三越、名古屋丸栄、名古屋松坂屋、神戸そごう、姫路やまとやしき等で、個展を多数開催。主として、楽焼と伊賀の陶技を使った作品を制作する
1976年昭和51年 国際交流基金の要請によって、ローマ日本文化会館主催の楽焼実演会を行う。
1986年昭和61年 第5回太閤窯小西平内茶陶展を名古屋松坂屋で開く。
サイズ:約直径5.1×高4.7cm
作者:小川長楽作
----------
【3代 (本名 幸夫)】号 裕起夫 長楽・松風軒
昭和22年 2代の長男に生まれる
昭和41年 工房・住所を山科清水団地に移り、師:長楽に師事
昭和44年 号 裕起夫にて創作活動に入る
昭和52年~57年の間、京都陶磁器青年会会長を務める
平成01年 2代長楽喜寿を記念して親子展を開催
平成03年 2代長楽 享年七十八歳にて永眠する
平成04年 幸夫氏が3代長楽を襲名。同時に醍醐寺座主麻生文雄硯師より「松風軒」を賜る
平成05年 徳仁親王と小和田雅子氏のご成婚を奉祝して、総本山醍醐寺の依頼により赤・白一双茶碗を献上
平成07年 開窯90年4を祝して仁和寺門蹟・吉田裕信鯨氏より「楽焼おちゃわんや」の暖簾を賜る
現在 日本工芸協議会副会長
(社)京都国際工芸センター常任理事
清水団地(協)常任理事
----------
箱:化粧箱
備考:在庫ありの場合(注文日~3日以内の発送可能)